家族葬と一般葬の違いを徹底解説|コラム(葬儀・葬式のお役立ち情報)|姫路市・太子町で葬式、葬儀、家族葬なら名古山葬儀式場、筑紫の丘斎場の受付窓口であるプライベートセレモニー
コラム一覧
公開日:2023.10.30 / 更新日:2025.08.05
家族葬と一般葬の違いを徹底解説
一般葬との違いで見る家族葬が人気の理由
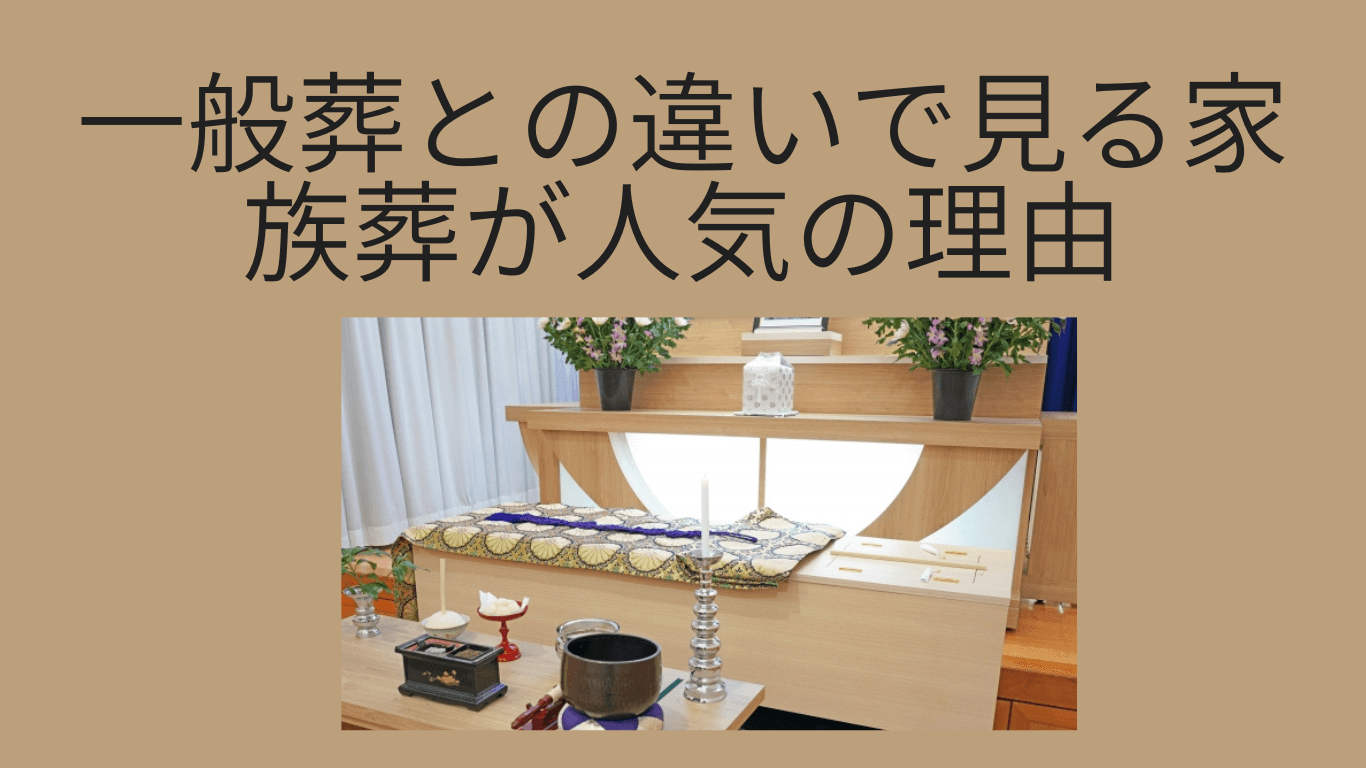
家族葬と一般葬は参列者数や費用、社会的役割が大きく異なります。本記事では最新の葬送トレンドと統計データを基に、両形式のメリット・デメリットを比較し、後悔しない葬儀を選ぶための判断ポイントを提示します。読めば「誰を招くか」「いくら掛かるか」「弔問対応をどうするか」など具体的な疑問が解消し、遺族と参列者双方が納得できる形を選択できるようになります。実際の費用相場やマナーの注意点も紹介するため、初めて喪主を務める方でも安心です。
1. 家族葬の基本知識
家族葬は「参列者をごく親しい範囲に限定し、ゆっくりとお別れの時間を持てる」ことを最大の特徴とする葬儀様式です。ここでは定義・流れ・費用の目安、そして家族葬が選ばれる社会的背景を詳しく解説します。
1.1 家族葬の定義
家族葬は、ご家族や近しい親族、故人と特別に親しかった友人のみで執り行う小規模な葬儀を指します。通夜・告別式という基本的な儀礼は一般葬と同様に行う一方、参列者を絞ることで進行を柔軟にできるのが特徴です。
1.1.1 招く範囲と人数
招待する範囲は各家庭によって異なりますが、下表が一般的な目安となります。
| 招待範囲 | 想定人数 | 備考 |
|---|---|---|
| 親族のみ | 5〜15名 | 二親等までが中心 |
| 親族+親しい友人 | 15〜30名 | 故人と交流の深かった友人を数名招くケース |
| 親族+生前の関係者 | 30〜40名 | 地域活動や趣味仲間などを限定的に招待 |
1.1.2 セレモニーの流れ
典型的な家族葬のスケジュールは以下の通りですが、参列者が少ないことで時間配分や演出を柔軟に変更しやすい点がメリットです。
- ご遺体搬送・安置
- 納棺・枕経
- 通夜式(1日葬の場合は省略または当日実施)
- 告別式・炉前読経
- 火葬・収骨
- 初七日法要・精進落とし(当日繰り上げが主流)
昨今では1日で通夜と告別式を行う「一日葬」や、宗教儀礼を簡略化してお別れの時間を重視する「直葬(ちょくそう)」を選ぶ遺族も増えています。
1.1.3 費用の目安
一般葬に比べて会場規模・接待費が抑えられるため、総額は50〜150万円程度がボリュームゾーンです。下表は主要費目と金額帯の一例です。
| 費目 | おおよその金額 | コストを抑えるポイント |
|---|---|---|
| 式場使用料 | 10〜30万円 | 小規模ホールや自宅を利用 |
| 祭壇・飾り付け | 5〜20万円 | 生花祭壇のサイズを調整 |
| 飲食・返礼品 | 5〜25万円 | 人数を限定し数量を最適化 |
| 宗教者へのお布施 | 5〜20万円 | 読経回数や戒名の格に応じ変動 |
| 火葬料・骨壷代 | 3〜10万円 | 自治体の公営火葬場で割安 |
平均費用の統計は葬儀、「お葬式の費用相場は。注意点と費用を抑えるコツも紹介します。」などで確認できます。
1.2 家族葬が選ばれる背景
なぜ家族葬がここまで広がったのか、社会情勢とライフスタイルの両面から見ていきます。
1.2.1 社会情勢の変化
高齢化と核家族化が進み、親族の居住地が分散した結果、大規模な一般葬を取り仕切る人的・時間的リソースが不足しやすくなりました。また2020年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大により、人が集まる行事を縮小する傾向が一気に加速しました。
1.2.2 ライフスタイルの多様化
仕事や趣味の形が多様化し「生前の交友関係が狭く深い」ケースが増えています。加えて、インターネットやSNSを通じて弔意を伝えられるようになり、葬儀の場で対面しなくてもお悔やみを表現できる環境が整備されたことも家族葬の追い風となりました。
このように、家族葬は現代の社会構造とライフスタイルに適応した葬儀形式として定着しつつあります。
2. 一般葬の基本知識
一般葬は、かつて日本で最も一般的だった葬儀形式で、故人や遺族とつながりのあるすべての弔問希望者を受け入れる点が特徴です。家族・親族だけでなく、友人・勤務先・取引先・地域住民まで幅広い人々が参列し、社会的な弔いの場として機能します。
2.1 一般葬の定義
一般葬とは、葬儀の参列範囲を限定せず、故人と縁のある人すべてに弔問の機会を提供する葬儀スタイルです。告別式の後に火葬を行う「通夜」「告別式」「火葬」という標準的な三つの儀礼を2日間で行うのが一般的です。
2.1.1 招く範囲と人数
告知方法は電話・メール・会社や自治会の連絡網・新聞の訃報欄など多岐にわたり、参列者数は50〜200名が目安です。大都市圏の企業経営者や著名人の場合、300名以上になるケースもあります。
2.1.2 セレモニーの流れ
標準的なタイムラインは以下の通りです。
- 通夜(18:00〜20:00):僧侶読経・焼香・通夜振る舞い
- 告別式(翌日10:00〜12:00):僧侶読経・弔辞・焼香
- 出棺・火葬(13:00〜15:00):火葬場にて炉前読経
- 収骨・精進落とし(15:30〜17:00):会食・喪主挨拶
遺族は弔問客対応や香典返しの手配など多くの役割を担うため、葬儀社のスタッフや受付係、世話役のサポートが不可欠です。
2.1.3 費用の目安
一般葬の総費用は平均150万〜200万円程度とされます(首都圏平均)。主な内訳は次の通りです。
| 費用項目 | 目安金額 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 葬儀基本料 | 50万〜80万円 | 祭壇・式場使用料・進行スタッフ |
| 飲食接待費 | 20万〜40万円 | 通夜振る舞い・精進落とし |
| 返礼品 | 10万〜30万円 | 会葬御礼品・香典返し |
| 宗教者謝礼 | 15万〜50万円 | 読経・戒名料など |
| 火葬・霊柩車 | 5万〜15万円 | 火葬料・車両費用 |
参列者数が多いほど会場規模・飲食・返礼品が増え、費用が高額化します。
2.2 一般葬の社会的役割
一般葬は個人の弔いにとどまらず、社会全体が故人を送り出す公的儀礼としての役割を果たします。ここでは二つの視点からその意義を整理します。
2.2.1 弔問の受け皿としての機能
故人と直接の面識があるか否かを問わず、誰もが哀悼の意を表す場を設けることで、参列者は心残りなく故人への別れを告げられます。また、遺族側も一度に弔意を受け止められるため、後日の個別対応負担を軽減できます。
2.2.2 企業や地域との関係維持
ビジネスパーソンや地域活動に積極的だった故人の場合、一般葬によって企業・自治会・町内会との結びつきを確認・維持し、遺族の今後の社会生活を円滑にする効果があります。弔電披露や弔辞の場は、故人の功績を公式に称える機会にもなります。
3. 家族葬と一般葬の違い一覧
下記では、家族葬と一般葬を比較するうえで特に質問が多い「参列者数」「進行とスケジュール」「費用構成」「遺族の心情」という四つの軸を中心に整理しました。
| 項目 | 家族葬 | 一般葬 |
|---|---|---|
| 平均参列者数 | 10〜30名 | 50〜200名 |
| 進行日程 | 1日葬・2日葬など柔軟 | 通夜+告別式の2日間が標準 |
| 費用相場 | 50万〜120万円 | 150万〜250万円 |
| 遺族の負担 | 少ない(弔問客応対が限定的) | 大きい(弔問客応対が多岐) |
3.1 参列者数の違い
誰を招くか、どの程度の人数になるかは葬儀全体の規模・費用・準備負担を左右する最重要ポイントです。
3.1.1 家族葬の参列者目安
3.1.1.1 親族のみ
配偶者・子ども・兄弟姉妹・孫など血縁者のみで10〜20名程度に留めるケースが主流です。弔問客応対の時間を最小限にできるため、「心身の負担軽減」を理由に挙げる遺族が増えています。
家族葬はどこまでが家族なの?家族葬の流れや費用についても紹介
3.1.1.2 親しい友人まで
故人と深く付き合いがあった友人やごく少数の職場関係者を含め20〜30名程度で執り行います。招待範囲を広げすぎないことでプライバシーを確保しつつ、思い出話を共有しやすい雰囲気が生まれます。
3.1.2 一般葬の参列者目安
3.1.2.1 会社関係者
勤務先の上司・同僚・取引先を含めると50〜100名以上になることもしばしばです。香典返しや受付体制を整える必要があるため、葬儀社スタッフや社内総務担当と連携して準備を進めます。
3.1.2.2 地域住民
自治会・町内会など地域社会との結び付きが強い場合、100名〜200名規模に達するケースもあります。
3.1.2.2.1 自治会・町内会
地域の習慣として弔問を「義理」と捉える傾向があり、香典のやり取りや受付名簿の作成が欠かせません。会葬礼状や返礼品の数を事前に読みにくい点が遺族の悩みどころです。
3.2 進行とスケジュールの違い
進行の柔軟性は家族葬が優位です。家族葬では通夜を省略した1日葬や、火葬のみを行う直葬といったオプションが選択可能です。一方、一般葬は参列者の都合を考慮し、通夜・告別式を標準の2日間で組むことが多く、受付・会食・会葬礼状配布などの進行が定型化しています。
3.3 費用構成の違い
費用差は主に「会場規模」「飲食接待」「返礼品」の三要素で生じます。
- 家族葬…小ホール利用、会食は精進落とし程度、返礼品数が少なく追加費用が生じにくい
- 一般葬…大ホール利用、通夜振る舞い+精進落とし、返礼品を人数分用意し、さらには会葬礼状・生花スタンド・マイクロバス代など人数比例で費用が増大
費用総額は地域差・宗派差もありますが、公益社の統計によると首都圏平均で家族葬113万円、一般葬214万円と約2倍の開きが見られます。
3.4 遺族の心情への影響
遺族が感じる心理的負担は参列者数の増減だけでなく、礼儀作法や時間的拘束にも大きく左右されます。
家族葬では「ゆっくりお別れできた」「気兼ねなく涙を流せた」という肯定的な声が多い一方、訃報を事後報告にしたことで「参列したかった」という知人からの苦言があるケースも報告されています。
対して一般葬では「社会的義務を果たせた安心感」が得られる反面、連絡・受付・返礼などに追われて「故人と向き合う時間が足りなかった」という遺族の感想が目立ちます。どちらを選択してもメリットとデメリットが存在するため、家族内で希望を共有し、優先順位を確認しておくことが重要です。
4. 家族葬が向いているケース
家族葬は「小規模・低負担・心のゆとり」を重視するご遺族に最適な葬送形式です。下記では、具体的にどのような状況で家族葬が選ばれやすいのかを整理し、判断材料を提示します。
| ケース | 適合度が高い理由 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 参列者が限られている | 訃報の範囲が狭く、香典・供花対応も簡略化できる | 親族・友人リストの把握、参列辞退への周知方法 |
| 費用を抑えたい | 会場・祭壇・返礼品の規模がコンパクトになり総額が下がる | プラン内容の比較、香典収入の見込み |
| 静かに見送りたい | 少人数のため時間的・心理的な負担が軽減 | 読経の有無、写真・音楽など演出面の自由度 |
4.1 参列者が限られている場合
故人の交友関係が親族中心、あるいは遺言で「身内だけで」と指定されている場合には家族葬が最適です。弔問客の受付・会計・返礼品準備などの動線が単純化し、遺族は儀礼よりも故人との時間に集中できます。
4.1.1 親族や親しい友人のみで営む
一般葬のように会社関係者や地域住民へ広く訃報を流さないため、連絡漏れによるトラブル防止策として「後日お別れ会を検討」する遺族も増えています。
4.1.2 遠方や高齢で参列が難しい親族が多い
参列の負担軽減を目的にオンライン配信を組み合わせる家族葬も普及しています。全葬連の調査によると、2023年は葬儀社の約4割がリモート参列サービスを導入しています。全日本葬祭業協同組合連合会
4.2 費用を抑えたい場合
厚生労働省「葬祭費の支給に関する調査」によると、一般葬の平均費用(通夜・告別式・火葬)は約140万円、家族葬は約100万円とされています。会場規模・返礼品数・スタッフ人件費を縮小できるため、30〜40%のコストダウンが期待できます。
4.2.1 必要最小限のアイテムで構成
・祭壇:生花祭壇を小サイズに
・会食:通夜振る舞いを軽食に変更
・返礼品:タオルや菓子折りなど単価を調整
4.2.2 香典辞退・供花辞退を併用
香典を受け取らない場合は会葬返礼品を不要にでき、さらに費用を削減可能です。ただし、辞退の文言は「ご厚志の儀ご辞退申し上げます」といった定型表現を案内状に明記し、誤解を招かないようにしましょう。
4.3 静かに見送りたい場合
精神的負担の軽減を優先し、儀礼的な挨拶や長時間の対応を避けたい遺族にとって家族葬は有効です。少人数のため最後の別れを心穏やかに過ごせるほか、参列者同士の距離が近く故人の思い出を分かち合いやすいという声もあります。
4.3.1 プライバシーを重視
芸能人や経営者が家族葬を選ぶ背景には、取材や参列者の集中を防ぎ「静けさ」を確保したい意向があります。報道対応は葬儀社または広報担当者を窓口に一本化するとスムーズです。
4.3.2 自由な演出が可能
映像上映・好きだった音楽・ドレスコードなど、少人数だからこそ演出の自由度が高まります。ガイドブックでは「個性を尊重した小規模葬儀」が推奨されています。
以上のように、家族葬は「人数」「コスト」「心情」の三軸で最適性が高いケースが多く、一般葬との違いを踏まえて選択することが重要です。
5. 一般葬が向いているケース
ここでは、家族葬ではなく一般葬を選択したほうが遺族・参列者の双方にとってメリットが大きい具体的な場面を解説します。まずは代表的なケースを一覧にまとめ、その後に詳細を掘り下げます。
| ケース | 一般葬が適している理由 | 想定される参列者 |
|---|---|---|
| 社会的つながりが広い | 故人の交友関係や肩書きが幅広く、参列希望者が多数いる | 会社関係者・取引先・地域自治会・友人知人 |
| 弔問客への配慮を重視 | 参列の場を設けることで感謝やお別れの機会を提供したい | 香典・供花を届けたい人、遠方からの会葬者 |
| 公的・社会的役職がある | 公務員・議員・企業経営者など公的立場の弔問需要に対応 | 業界団体・行政関係者・報道機関 |
| 宗教儀礼を重視 | 菩提寺や檀家として慣習どおりの儀式を行いたい | 檀家仲間・寺院関係者・宗教団体 |
5.1 社会的つながりが広い場合
故人が会社役員・医師・教員・地域の役員など、社会的ネットワークが広い場合、家族葬では参列者を制限しきれず、かえって混乱を招く可能性があります。一般葬なら以下のようなメリットがあります。
5.1.1 会社・取引先との関係を重視
訃報を社内外へ正式通知し、弔問を受け入れることで、故人への敬意と企業としての礼節を示せます。挨拶や会葬礼状を通じて業務上の引き継ぎや今後の連絡窓口を明確にできるのも利点です。
5.1.2 地域コミュニティとの絆を大切にしたい
自治会や町内会、消防団など地域社会で要職を担っていた故人の場合、一般葬を行うことで地域の仲間が最後のお別れをしやすくなり、遺族も近隣との関係を良好に保てます。
5.2 弔問客への配慮を重視する場合
「香典を辞退しない」「供花を受け付ける」「弔電を披露したい」といった要望がある場合、一般葬のほうが参列者の気持ちに応えやすい形式です。
5.2.1 故人への感謝の場を設けたい
教え子、患者、取引先など大勢の人が故人へ感謝を伝えたいと考えているとき、一般葬なら焼香・献花の時間を十分に取り、遺影や思い出の写真を展示することで参列者の満足度が高まります。
5.2.2 香典辞退をしない方針のとき
香典を辞退しない場合は、参列者の人数が費用補填につながり、式場・祭壇規模を確保しやすくなります。香典返しを通じて遺族が直接お礼を述べる機会も得られます。
5.3 公的・社会的役職がある場合
公務員や地方議会議員、医師会・商工会議所の要職など公の立場で活動していた故人は、一般葬で公的弔問の場を設けることが慣例的に求められます。参列者を限定すると「呼ばれなかった」という不満や後日の弔問殺到につながりかねません。
5.4 宗教儀礼を重視する場合
浄土真宗や日蓮宗など、檀家としての付き合いが深い寺院があるケースでは、読経や導師の複数名出仕など一定の儀式規模が想定されます。家族葬にしようとしても「お寺と檀家のつながり」を守るために一般葬を勧められることがあります。
以上のように、社会的・宗教的な要請が大きい場合や、弔問客への配慮を最優先したい場合には一般葬が最適と言えます。近年の調査でも、会社役員や地域功労者の葬儀では一般葬が依然として主流である旨が報告されています(参考:鎌倉新書「お葬式に関する全国調査2023」)。
6. 家族葬を行う前の注意点
6.1 参列辞退の連絡方法
家族葬は招待する範囲を明確に限定するため、訃報を受けた人すべてに参列をお願いしないケースが多い。参列を辞退する場合でも、故人や遺族との関係を損なわないよう丁寧な連絡が必要になる。
| 連絡手段 | 主な対象 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 電話 | 親族・親しい友人 | 肉声で思いを伝えられる | 時間帯に配慮し、要点を簡潔に |
| メール/LINE | 仕事関係者・遠方の知人 | 一斉送信で情報を統一できる | 敬語表現を誤ると誤解を招く |
| 弔電 | 高齢者・礼儀を重んじる層 | 形式的な礼節を保てる | 投函から到着まで日数がかかる |
辞退の文面例は「通夜・告別式は近親者のみで執り行います。誠に勝手ながらご弔問・ご香典の儀はご辞退申し上げます。」のように、参列・香典双方の辞退意思を明確にすることが重要である。
6.2 香典や供花の辞退表現
香典や供花を辞退する場合、表現を誤ると「受け取りを拒否された」と相手に不快感を与えかねない。All About「香典返し・辞退のマナー」を参考に、柔らかな言い回しを用いると良い。
| 断りたい項目 | 推奨フレーズ | 避けたいフレーズ |
|---|---|---|
| 香典 | 「ご厚志につきましてはご辞退申し上げます」 | 「お金はいりません」 |
| 供花 | 「勝手ながら供花の儀も遠慮させていただきます」 | 「花は不要です」 |
| 弔電 | 「弔電もご遠慮申し上げます」 | 「電報も要りません」 |
6.3 トラブルを防ぐポイント
6.3.1 親族間の認識合わせ
人数制限や予算の決定は、最初の段階で血縁の近い親族へ共有し、必ず同意を得ておくと後々の不満を防げる。LINEグループやオンライン会議を活用すれば遠方の親族とも調整しやすい。
6.3.2 近隣・自治会への配慮
家族葬でも霊柩車の出入りや会葬礼状の配達などで近隣に迷惑がかかる場合がある。事前に自治会長や隣家へ簡単な挨拶を行い、駐車場の利用や騒音時間帯を共有しておくと良好な関係を保てる。
6.3.3 宗教者との打合せ
菩提寺がある場合は「家族葬にしたい」旨を早めに相談し、読経料(お布施)の目安や戒名の有無を確認する。菩提寺が遠方であればオンラインで法話や読経を依頼する方法もある。
6.3.4 事前見積もりの確認
いい葬儀「家族葬の費用ガイド」にもある通り、プラン料金以外に以下の追加費用が発生しやすい。
- 火葬料・骨壺代
- ドライアイス追加分
- 式場延長料
- 僧侶へのお布施・車代
契約前に見積書に含まれる項目と別途費用になる項目を色分けしてもらうことで、総額が当初予算を超えないか確認できる。
6.3.5 公的手続きとアフターサービス
死亡届の提出、健康保険証の返却、年金の手続きなどの公的手続きは原則7日以内に行う必要がある。葬儀社が代行してくれる場合もあるが、遺族自身が必要書類を準備しなければならないことが多い。あわせて、遺影写真の加工データや位牌の管理、四十九日までの法要日程も決めておくと後の負担が軽減される。
6.3.6 弔問客へのフォロー
参列を辞退しても弔意を示したいという友人・同僚は多い。後日設ける「お別れ会」や「偲ぶ会」の開催予定を伝えたり、供花・香典を受け取らない代わりにメモリアル寄付の案内を同封するなど、代替案を示すと感謝の意が伝わりやすい。
7. まとめ
家族葬と一般葬の違いは参列者数・進行・費用に大別される。縁故が限られ費用を抑え静穏を望むなら家族葬、社会的付き合いが広く弔問客への配慮を優先するなら一般葬が適切。いずれも事前に参列辞退や香典の取扱いを明確に伝達し、誤解やトラブルを防ぐことが重要だ。葬儀社との打合せでは、プラン内容と見積書を細部まで確認し、追加費用や会場規模が希望と合致しているかをチェックしよう。安心して最期の時間を見送るために準備を万全に。
ご相談・お申し込み
まずはお電話でご相談ください。もちろん相談だけでも大丈夫です。
お客様のご不安を解消するために、専任のスタッフが対応いたします。少しでもお役に立てればと思います。
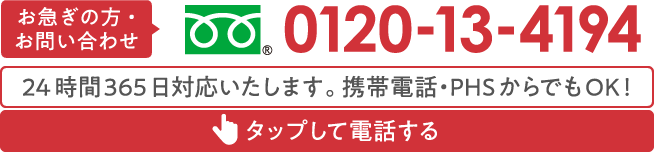

 私たちは、最期まで安心して暮らせる
私たちは、最期まで安心して暮らせる